第7回 唾液の力を知っていますか
令和02年05月15日

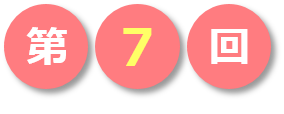
「皆さん、歯ブラシをしていますか?」と聞かれて、「してないよ。」という方は今の日本にはまずいらっしゃらないでしょう。世界に類を見ない清潔な国民の日本人は有名です。
しかし、北欧などと比べると少し後れをとっている感じが否めないのは、保険制度の問題もあるでしょうが、ここではそれはおいといて、歯ブラシ習慣に少し目を向けてみましょう。
生活習慣病という言葉がありますが、歯ブラシもまさに生活習慣です。歯ブラシを口の中に最初に入れる位置、磨く順番、時間、歯磨剤の量まで何も考えずにおこなっていませんか?
日本では一日3回たべたら、3分以内に、3分間歯を磨きましょう、という50年も昔の「3.3.3運動」が今も浸透しています。
しかし最近では、食後すぐに歯を磨くと歯を痛めたり逆効果になるとの意見も出ています。これは、糖質を含む食事をすると人の口の中は、phが酸性に傾き、 歯の表面からはミネラル(カルシュウムやリン)が放出され一時的に歯の表面の硬いエナメル質の結晶構造が緩むため、少し歯の表面が弱くなります。それを、唾液が1時間程度かけて元の硬さに戻しています。(再石灰化)
特に歯の柔らかくなった時に、歯磨剤をつけて、歯ブラシでこすると、歯の表面や根元が傷つきやすくなるのです。ですので、唾液が再石灰化をする時間を少し与えてあげてからお掃除の方がいいと思います。
当然、食後に歯の間に詰まった食べかすは気になるでしょうし、前歯などにのりやネギがはさまっていては笑えません。それを放置しろとは言いません。そんなときはまず、歯の間の食べかすをとって、歯間に唾液の流れを良くするようにしてあげましょう。
そんなときデンタルフロスが活躍するのですが、日本でのデンタルフロス使用率は25%程度、歯間ブラシは20%以下と言った状況です。歯垢除去的にも頬の粘膜、唇、舌などでいつも接触して汚れのつきにくい歯の表面を歯ブラシを使って磨くより、 歯ブラシの届きにくい歯と歯の間の歯垢をとって唾液の流れを良くしてくれます。かつキシリトールガムでも噛んでさらに唾液の出を促し、そのあとで、今まで通りの歯磨き(ちゃんと衛生士さんに指導を受けた方法がいいですが)を行いましょう。
口の中の細菌と全身疾患(糖尿病、心臓疾患、高血圧、脳梗塞、肺炎など)との関係もどんどん解明されてきています。唾液には、食後柔らかくなった歯を硬くしたり、全身疾患を起こす歯垢(プラーク)を取れやすくしてくれます。
虫歯や歯周病の予防というよりは、全身の健康という観点からも唾液には驚く力があります。この力が生かせるような、生活習慣に変えてみてはどうでしょう。
|
日本歯科医師会PRキャラクター「よ坊さん」 |
徳島県歯科医師会 常務理事 田岡 計久 先生 |
- 第29回 歯科医師だけじゃない!歯科医療を支える専門職~歯科衛生士と歯科技工士のお仕事~
- 第28回 周術期等口腔管理について
- 第27回 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
- 第26回 訪問歯科における口腔ケアの役割
- 第25回 歯科用金属アレルギーとは
- 第24回 気になる子どもの『お口ポカン』
- 第23回 上手に歯医者さんにかかりましょう
- 第22回 口腔内不定愁訴(こうくうないふていしゅうそ)について
- 第21回 妊娠中は歯科治療できるの?
- 第20回 健康と健口!体の不思議
- 第19回 子供のむし歯の特徴
- 第18回 口腔がんについて
- 第17回 歯科医院でお口の健康診断を受けていますか?
- 第16回 災害時の口腔ケア ~口腔ケアで命を守ろう~
- 第15回 周術期の誤嚥性肺炎の予防
- 第14回 卒乳のタイミングと方法
- 第13回 自分のために 歯科医院でブラッシング指導を受けてみましょう
- 第12回 マイナス1歳からのむし歯予防
- 第11回 訪問歯科診療について
- 第10回 「小児における口腔機能発達不全」とは
- 第9回 8020(ハチマルニイマル)と根面う蝕
- 第8回 withコロナと歯科治療
- 第6回 オリンピックイヤー 注目されるスポーツ歯科
- 第5回 最近の子どものむし歯状況
- 第4回 歯周病と糖尿病
- 第3回 周術期の医科歯科連携
- 第2回 歯周病と全身疾患
- 第1回 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア

