第15回 周術期の誤嚥性肺炎の予防
令和04年05月27日

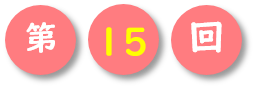
周術期の誤嚥性肺炎の予防
誤嚥性肺炎という用語は古くから使われていますが、定義や診断基準は明確ではありません。
明らかな誤嚥の確認または嚥下機能障害の存在と肺の炎症所見の確認によって診断されます。
つまり、嚥下機能障害を確認した患者に発症する肺炎で、明らかな他の原因が考えられない場合誤嚥性肺炎と考えます。
通常の誤嚥性肺炎は食事などでむせるような「顕性誤嚥」から発症するよりも、頻回に起こる「不顕性誤嚥」の結果として多く発症します。
不顕性誤嚥は主に夜間に鼻腔、口腔、咽喉頭分泌物を誤嚥するものです。
誤嚥性肺炎の発症過程は、鼻腔や口腔内の微生物が気道へ吸引・誤嚥され、肺炎を引き起こすというものです。
微生物の種類や量に関しては、鼻腔や口腔内の衛生状態が問題となります。
肺への吸引・誤嚥過程には嚥下反射の障害が関与し、肺炎に至る過程では局所や全身の防御能が重要であり、咳反射の障害や全身免疫力の低下が問題となります。
不顕性誤嚥による誤嚥性肺炎の対策として、
➀就寝時頭位挙上、日中の座位保持、②口腔内細菌叢の改善、③歯科的介入による口腔内保清、④投薬による嚥下反射改善、⑤意識レベルの維持、が挙げられます。
歯科の専門的口腔ケアの実際としては、唾液腺マッサージと脱感作の後、咽頭部と舌の痰を除去し、歯牙のブラッシングを行います。
口腔粘膜全体をスポンジブラシや濡れたガーゼまたは不織布を使って清拭し、リフレケアなどを塗布します。痰が多い場合は咽頭部の痰を吸引します。
⑴肺炎の活動期で痰が多く、意識下での喀咳も困難な時は頻回な吸引が必要となります。
⑵乾燥が強い時は、施術前に唾液腺マッサージと保湿剤を使用し、施術後も保湿剤を使用します。
⑶歯間部の汚れは歯間ブラシを使用します。
患者が口腔内を触られることに精神的不安がある時は、口腔ケアの様子を鏡で見てもらいながら説明し、安心して口腔ケアを受けられるように心がけることも重要です。
また家庭において家族が口腔ケアをする場合は、口腔ケアのポイントを理解してもらうことで精神的負担を軽減することも大切と思われます。
日本歯科医師会PRキャラクター「よ坊さん」 | 徳島県歯科医師会 理事 上田 美佳 先生 |
- 第30回 成人の歯周病検診が約10年ぶりに改定されます ~歯と口の健康アップと機能の維持を自らの気づきからめざしていただくために~
- 第29回 歯科医師だけじゃない!歯科医療を支える専門職~歯科衛生士と歯科技工士のお仕事~
- 第28回 周術期等口腔管理について
- 第27回 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
- 第26回 訪問歯科における口腔ケアの役割
- 第25回 歯科用金属アレルギーとは
- 第24回 気になる子どもの『お口ポカン』
- 第23回 上手に歯医者さんにかかりましょう
- 第22回 口腔内不定愁訴(こうくうないふていしゅうそ)について
- 第21回 妊娠中は歯科治療できるの?
- 第20回 健康と健口!体の不思議
- 第19回 子供のむし歯の特徴
- 第18回 口腔がんについて
- 第17回 歯科医院でお口の健康診断を受けていますか?
- 第16回 災害時の口腔ケア ~口腔ケアで命を守ろう~
- 第14回 卒乳のタイミングと方法
- 第13回 自分のために 歯科医院でブラッシング指導を受けてみましょう
- 第12回 マイナス1歳からのむし歯予防
- 第11回 訪問歯科診療について
- 第10回 「小児における口腔機能発達不全」とは
- 第9回 8020(ハチマルニイマル)と根面う蝕
- 第8回 withコロナと歯科治療
- 第7回 唾液の力を知っていますか
- 第6回 オリンピックイヤー 注目されるスポーツ歯科
- 第5回 最近の子どものむし歯状況
- 第4回 歯周病と糖尿病
- 第3回 周術期の医科歯科連携
- 第2回 歯周病と全身疾患
- 第1回 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア

