第9回 8020(ハチマルニイマル)と根面う蝕
令和02年11月11日

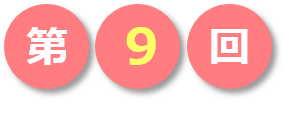
8020運動は、「80歳になっても自分の歯で食べることができるように20本以上の歯を保とう」と平成元年から始まった運動です。
当初は、80歳で20本以上の歯が保たれている人は7%だったのに対し、平成28年の歯科疾患実態調査では51.2%まで達しています。徳島県歯科医師会では、毎年8020を達成された方々に祝意を表していますが、この運動の認知度が浸透するとともに、平成11年の39名から令和元年には383名まで増加しています。
2016年に、日本歯科総合研究機構が、医科と歯科を受診した患者さん230万件のデータをナショナルデータベースから集計・分析しました。その結果、すべての年齢層で20本以上の歯が保たれている人は19本以下の人に比べ、医科の医療費が低い、つまりより健康だということが示されました。これは8020運動の理念が正しかったことを裏付けています。
しかしながら、歯を失う高齢者が減少していることによって、高齢者のむし歯が増加するという新たな課題が生じています。
歯は、頭の部分(歯冠)と根っこの部分(歯根)があります。歯根のむし歯の主な原因は、歯根が歯ぐきから露出することです。健康な状態では、歯根は歯ぐきに覆われていますが、歯ぐきが下がりむき出しになると、そこにプラーク(歯垢)がたまり、むし歯になるリスクが高くなってしまいます。露出した歯根がむし歯になりやすい理由は、歯冠と歯根の構成されている成分や組織、硬さに違いがあるためです。
歯冠は硬いエナメル質に覆われていますが、根面はエナメル質とは異なり、より硬度の低い象牙質で構成されています。エナメル質と象牙質ではpHが異なり、象牙質は口の中が少し酸性に傾くだけで、酸によって容易に溶けてしまいます。また、加齢とともに口の機能や環境の変化も起こります。なかでもむし歯と関連が深いものでは、唾液量の減少や口腔乾燥症の発現があげられます。
唾液には、むし歯菌が作る乳酸を中和して、乳酸が歯の表面を溶かすことを防ぐ力があります。また、唾液の中に含まれるカルシウムやリン酸などの無機質には、乳酸が歯の表面を溶かし始めた初期の段階で、歯の表面を修復する力があります。さらに、唾液には歯についた食べカスを洗い流してくれる洗浄作用もあります。
唾液量が減少したり口の中が乾いたりすると、こういった作用が弱くなり、むし歯になりやすくなってしまいます。
根面う蝕は、歯を取り囲むように輪っか状に進行するため、治療がしづらいことが特徴ですが、そのまま放置していると、根面からポキっと歯が折れてしまう可能性もあります。
いつまでも自分の歯で噛み、健康な生活を送るためにも、根面う蝕を予防する口腔清掃と唾液の分泌を維持することが大切となります。
※根面う蝕とは歯の根元(歯根)にできる虫歯のこと
|
日本歯科医師会PRキャラクター「よ坊さん」 |
一般社団法人 徳島県歯科医師会 常務理事 柴田 享 先生 |
- 第30回 成人の歯周病検診が約10年ぶりに改定されます ~歯と口の健康アップと機能の維持を自らの気づきからめざしていただくために~
- 第29回 歯科医師だけじゃない!歯科医療を支える専門職~歯科衛生士と歯科技工士のお仕事~
- 第28回 周術期等口腔管理について
- 第27回 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
- 第26回 訪問歯科における口腔ケアの役割
- 第25回 歯科用金属アレルギーとは
- 第24回 気になる子どもの『お口ポカン』
- 第23回 上手に歯医者さんにかかりましょう
- 第22回 口腔内不定愁訴(こうくうないふていしゅうそ)について
- 第21回 妊娠中は歯科治療できるの?
- 第20回 健康と健口!体の不思議
- 第19回 子供のむし歯の特徴
- 第18回 口腔がんについて
- 第17回 歯科医院でお口の健康診断を受けていますか?
- 第16回 災害時の口腔ケア ~口腔ケアで命を守ろう~
- 第15回 周術期の誤嚥性肺炎の予防
- 第14回 卒乳のタイミングと方法
- 第13回 自分のために 歯科医院でブラッシング指導を受けてみましょう
- 第12回 マイナス1歳からのむし歯予防
- 第11回 訪問歯科診療について
- 第10回 「小児における口腔機能発達不全」とは
- 第8回 withコロナと歯科治療
- 第7回 唾液の力を知っていますか
- 第6回 オリンピックイヤー 注目されるスポーツ歯科
- 第5回 最近の子どものむし歯状況
- 第4回 歯周病と糖尿病
- 第3回 周術期の医科歯科連携
- 第2回 歯周病と全身疾患
- 第1回 誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア

