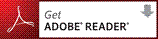申請方法・提出先
紙の申請書を郵送提出いただく方法と、電子申請サービス(令和8年1月13日サービス開始)を利用してオンライン申請する方法があります。
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出してください。(必着)
紙の申請書は、お住いの都道府県協会けんぽ支部へご郵送ください。
電子申請サービスを利用して申請する場合は、提出先をお選びいただく必要はございません(社会保険労務士の方は支部指定が必要です)。
申請書様式
被保険者の記号・番号をご記入された場合は個人番号(マイナンバー)のご記入は不要です。
 申請書 (手書き用) (手書き用記入例)
申請書 (手書き用) (手書き用記入例)
(入力用)※必ずPDFファイルをダウンロードし、Adobe Readerにより開いてください。(操作方法は「入力用申請書の利用案内」をご確認ください)
このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。
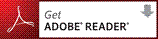
制度
収入の基準
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。
ただし、以下の基準により被扶養者に認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者※2を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者※2を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者※2を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
※1 扶養認定日が属する年の12月31日時点での年齢となります。
※2 配偶者とは被保険者の「夫」「妻」「内縁の夫」「内縁の妻」を指します。
添付書類
退職日が確認できる書類(任意)
次のいずれかを添付してください。
・退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピー等、事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類
・申出書の健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)への記載
※添付(記載)がない場合でも、ご提出いただくことはできますが、協会での手続きは、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けた後に行います。
口座振替により保険料の納付を希望する場合
被扶養者となる方がいる場合
〇被扶養者となる方が国内居住
次に該当する書類を添付してください。具体的な確認書類については、確認書類の具体例をご覧ください。
| | 在職時より引き続き被扶養者となる場合 | 任意継続の資格取得と同時に
新たに被扶養者となる場合 |
マイナンバーによる情報照会の実施を
希望する場合 | マイナンバーによる情報照会の実施を
希望しない場合 |
| 被保険者と同居 | ・添付書類不要(※) | ・収入を証明する書類 | ・続柄を証明する書類
・収入を証明する書類
・同居していることを証明する書類 |
| 被保険者と別居 | ・仕送りの事実と1回あたりの
仕送り額が確認できる書類 | ・収入を証明する書類
・仕送りの事実と1回あたりの
仕送り額が確認できる書類 | ・続柄を証明する書類
・収入を証明する書類
・仕送りの事実と1回あたりの
仕送り額が確認できる書類 |
※マイナンバーによる照会の結果、情報を取得できない場合は、添付書類の提出が必要になる場合があります。
〔情報を取得できない場合〕
・協会けんぽでマイナンバーが未収録の場合
・照会先の市区町村等から収入等に係る回答を得ることができなかった場合 等
(確認書類の具体例)
①続柄を証明する書類:戸籍謄(抄)本、または、世帯全員が記載されている住民票
②収入を証明する書類:所得証明書、(非)課税証明書、給与証明書、離職票のコピー、直近の年金額改定(振込)通知書のコピー、確定申告書のコピー(青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支報告書」等、収入の内訳が確認できる書類が必要)等 → 16歳未満の場合は添付不要(学生の場合でも16歳以上の方は添付が必要)
③同居していることを証明する書類:同居が確認できる、世帯全員が記載されている住民票
④仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認できる書類:預金通帳のコピー、現金書留控えのコピー等 → 16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要 |
〇被扶養者となる方が海外居住
- (国内居住である場合は添付書類に加えて)海外特例要件に該当することの確認書類
| 海外特例要件 | 確認書類 |
| ①海外に留学している(留学) | 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書の写し |
②海外に赴任する被保険者に同居する家族
(同行家族) | 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行
する居住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の
目的で一時的に海外に渡航する家族(特定活動)
| 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、
ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との
身分関係が生じた家族(海外婚姻等)(海外赴任中に生
まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など) | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤上記①~④まで掲げるもののほか、渡航目的でその他の事情を考慮して
日本国内に生活の基礎があると認められる家族 | 個別に判断 |
※確認書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がされた翻訳文の添付が必要です。
被保険者のマイナンバーを記載した場合
本人確認書類貼付台紙
被保険者のマイナンバーは、資格情報のお知らせ等に記載されている記号と番号が不明の場合のみご記入ください。
<ご注意ください>
こちらは紙の申請に限定した添付書類の取扱いです。
電子申請では、マイナンバーが記載された画像はアップロードいただけません。
なお、代理人が提出する場合は、以下の書類も併せて必要です。
〈法定代理人の場合〉
・戸籍謄本、その他法定代理人を証明する書類等
・写真付き身分証明書のコピー
〈 任意代理人の場合〉
・委任状(任意様式〉
・写真付き身分証明書のコピー
※社会保険労務士が提出を代行する場合は、申請書等の提出代行欄に社会保険労務士のゴム印等記載があれば、委任状は不要です。また、代理人の身元確認書類は社会保険労務士証票のコピーでも構いません。
提出期限
退職日の翌日から20日以内
注意事項
〇人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動がある場合の特例について
- 人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者等の場合は180万円)以上となっても、事業主証明を添付することにより、原則、連続2回まで被扶養者の認定が可能になります。 (詳しくは「年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省HP)」)

 申請書
申請書