令和7年1月 ≪お酒との上手なつきあいかた≫
令和07年01月16日
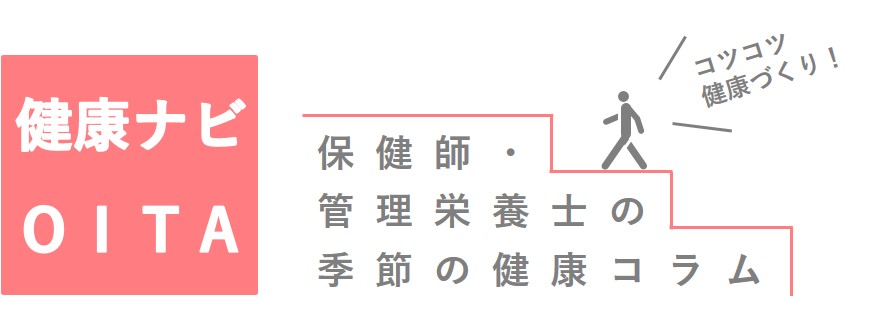
これまで「適量であれば、健康に支障はない」と考えられてきたアルコールですが、最新の研究で少量の飲酒でも生活習慣病やがんなどのリスクになることが明らかになり、「飲酒量は少なければ少ないほど健康に与える害が少ない」ことがわかってきました。
*高血圧(男女ともに)や出血性脳卒中(女性)、胃がん(男性)、食道がん(男性)は少しでも飲酒するとリスクが高まると考えられています。(我が国における疾病別の発症リスクと飲酒量より)
健康で長くお酒を楽しむためには、今よりも少しでも飲酒量を減らしておくほうがよさそうですね。
2024年2月に厚生労働省から、アルコールのリスクに対する理解の普及と、不適切な飲酒を減らすことを目的に、「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」が公表されました。
このガイドラインを参考にお酒を飲むときに心がけたいことをお伝えします。
~お酒を飲むときに心がけたいこと~
・みずからの飲酒状況などを把握する
純アルコール量(g)をチェックしてみましょう。
・あらかじめ量を決めて飲酒をする
自分で飲む量を決めて飲むことが、飲酒行動の改善につながります。
・飲酒前や飲酒中に食事をとる
血中アルコール濃度を上がりにくくさせて、お酒に酔いにくくする効果があります。
・飲酒の合間に水を飲む
アルコールをゆっくり分解、吸収できるようにします。
・1週間のうち、飲酒しない日を設ける
休肝日をつくろう!
*生活習慣病のリスクを高める1日あたりの飲酒量(純アルコール量)
男性40g以上・女性20g以上です。
この量が適量というわけではなく、これ以上は生活習慣病のリスクが高まるという量です。
*純アルコール量20gのお酒の目安量
・ビール(5%)ロング缶1本(500ml)
・日本酒(15%)1合(180ml)
・チューハイ(7%)1缶(350ml)
・ワイン(12%)グラス2杯(200ml)
・焼酎(25%)グラス1/2杯弱(100ml)
・ウイスキー(43%)ダブル1杯(60ml)
*純アルコール量の算出方法についてもお伝えします。
お酒に含まれる純アルコール量は、
「純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」で表すことができます。
飲酒をする場合には、お酒に含まれる純アルコール量を認識し、自身のアルコール摂取量を把握することで、健康管理に活用しましょう。
年末年始は飲み会が増える時期ではありますが、いつもよりは飲酒の量を減らして、休肝日をつくり上手にお酒とつきあいましょう。
- 令和6年10月 ≪あなどれない脂肪肝≫
- 令和6年11月 ≪座りすぎにはご注意ください≫
- 令和6年12月 ≪腸内環境を整えて感染症を防ごう!≫
- 令和7年2月 ≪あなたの血圧、大丈夫?≫
- 令和7年3月 ≪春に増えるメンタル不調を防ぐには≫
- 令和7年4月 ≪理想的な食事バランスについて≫
- 令和7年5月 ≪主食について≫
- 令和7年6月 ≪主菜について≫
- 令和7年7月 ≪副菜について≫
- 令和7年8月 ≪気を付けよう!熱中症予防!≫
- 令和7年9月 ≪座りっぱなしの生活から卒業!体も心も軽くなる運動の効果≫
- 令和7年10月 ≪意外とお手軽♪すき間時間でLet’s筋トレ≫
- 令和7年11月 ≪運動嫌いでも大丈夫! +(プラス)10(・テン)から始めましょう≫
- 令和7年12月 ≪休養について≫
- 令和8年1月 ≪睡眠対策法について≫
