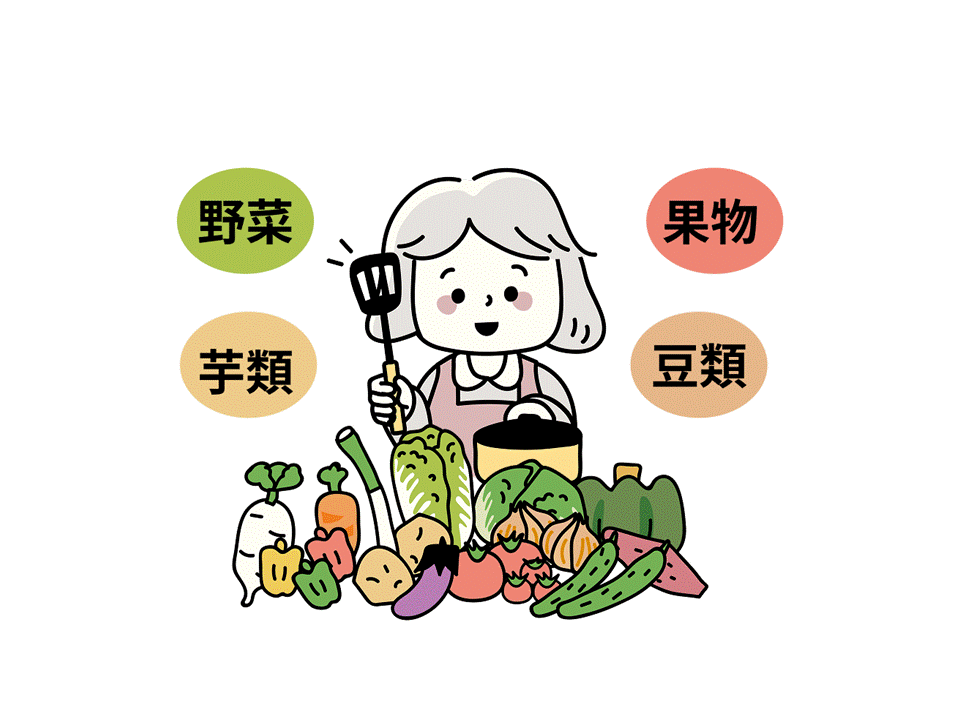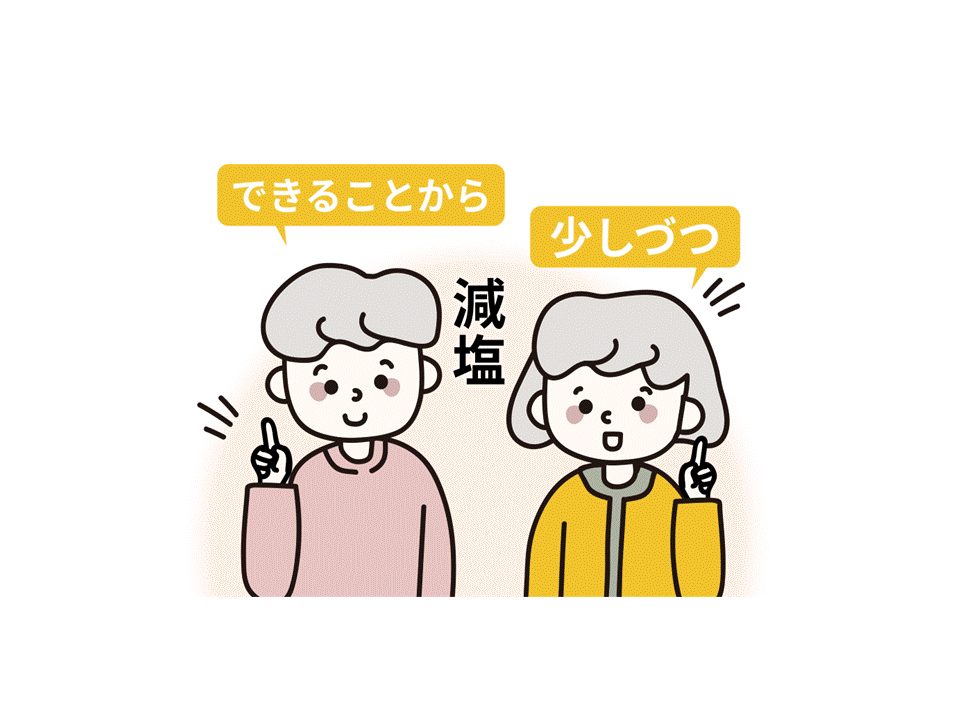塩分、ちょっと摂りすぎていませんか?

私たちの食生活には、思っている以上に多くの塩分が含まれています。
ラーメンや漬物だけでなく、パンやハム、冷凍食品、外食の定食など、身近なメニューにも意外と多くの塩分が使われています。
塩分を摂りすぎると、高血圧のリスクが高まり、動脈硬化や心疾患、脳卒中などの原因になることも。
だからこそ、毎日の食事で少しずつ「減塩」を意識することが、将来の健康を守る第一歩になります。
1日の塩分、どのくらいが適量?
厚生労働省が推奨する1日の塩分摂取量の目標は以下のとおりです。
●成人男性:7.5g未満
●成人女性:6.5%未満
ラーメン1杯には約6gの塩分が含まれています。気づかないうちに1日の目安を超えてしまうことも珍しくありません。
また、高血圧や心臓病などの既往歴がある方の場合は、1日6g未満が望ましいとされています。
外食や加工食品が多い食生活では、減塩を意識しない限り、簡単に過剰摂取につながってしまいます。
実はこんなところにも...”かくれ塩分”に注意
塩辛い味がしないからといって、塩分が少ないとは限りません。普段何気なく口にしている食品にも、実は多くの塩分が含まれていることがあります。
たとえば...
●パン(1枚あたり0.8~1.2g程度)
●ハム・ベーコンなどの加工肉
●インスタント食品やカップ麺
●ドレッシングやソース、めんつゆ
●コンビニ弁当や外食の定食メニュー
これらは「味の濃さ」ではなく「製造工程や保存のため」に塩分が使われていることが多く、
自覚しにくい塩分過多の原因になります。
知らないうちに1日の目安を超えてしまわないよう、食材選びや調味料の使い方に注意しましょう。
今日からできる、減塩のコツ
減塩は「味を薄くする」ことだけではありません。
工夫次第で、美味しさを保ちつつ自然に塩分を減らすことができます。
1.調味料は「かける」より「つける」 しょうゆやソースはかけるより、少量を小皿に出してつけて食べるほうが塩分を抑えることができます。
2.だしや香味野菜で”風味”をプラス 昆布やかつおだし、しょうが、にんにく、しそ、柚子などを使えば、塩分を減らしても満足のある味わいに。
3.漬物・汁物は”少しだけ” 味噌汁やラーメンのスープは、全部飲まずに残すだけでも塩分カットになります。漬物も食べる量を意識しましょう。
4.加工食品はなるべく控える
ハムやベーコン、カップ麺、レトルト食品などは塩分が高め。手作りや減塩表示の食品を選ぶようにしましょう。
5.減塩表示の商品を活用
最近では、減塩タイプの調味料や食品が多く販売されています。上手に取り入れるのもひとつの手です。
減塩だけじゃない。”ナトカリ比”を意識しましょう
減塩と並んで大切なのが「ナトカリ比(ナトリウムとカリウムのバランス)」です。
ナトリウム(=塩分)を減らすだけでなく、カリウムをしっかり摂ることで、より効果的に血圧をコントロールできるといわれています。
カリウムは、余分なナトリウムを体外に排出するはたらきがあり、血圧を下げる作用があります。
つまり「塩を控える+カリウムを摂る」という組み合わせが理想です。
カリウムを多く含む食品例
●野菜(ほうれん草、ブロッコリー、トマト など)
●果物(バナナ、キウイ、アボカド など)
●芋類(じゃがいも、さつまいも)
●豆類、海藻類 など
※腎臓に病気のある方は、カリウムの摂取制限が必要な場合があります。
医師の指導を受けましょう。
減塩は、無理せず「続ける」ことが大切です
塩分の摂りすぎは、気づかないうちに私たちの体に負担をかけ、将来的な病気のリスクを高めてしまいます。
ただ、減塩は「味気ない」「我慢するもの」ではありません。
だしや香味野菜を活用したり、調味料の使い方を工夫したりと、楽しみながら取り組むことができます。
大切なのは、一度に完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ、毎日の習慣として取り入れていくこと。
減塩は、未来の自分や家族の健康への”やさしい”投資”です。
きょうから、あなたの食卓に減塩の一歩を。