
カキには脂質の代謝やたんぱく質の合成に必要な亜鉛が多く含まれています。バランスのとれた食事で肝臓をいたわりましょう。
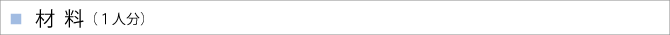
|
<下味>
- おろし生姜……5g
- 酒……大さじ1(15g)
- こしょう……少々
- ブロッコリー(花と茎あわせて)……50g
- ごま油……小さじ1(4g)
- 長ねぎ……10g
<合わせ調味料>
- オイスターソース……小さじ1/2(3g)
- しょうゆ……小さじ1/2(3g)
- 水……大さじ3(45g)
<水溶き片栗粉>
- 片栗粉……小さじ1/2(1.5g)
- 水……小さじ1(5g)
|
 |
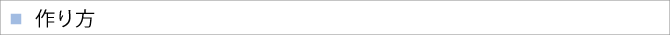
 |
カキは塩(分量外)をふりかけてぬめりをとり、流水でよく洗い、キッチンペーパーで水気を取る。下味の材料をボウルに入れて混ぜ、カキを入れる。 |
 |
合わせ調味料の材料を小さめの器に入れ、混ぜておく。別の器に入れた片栗粉に水を加え、混ぜておく(水溶き片栗粉)。 |
 |
ブロッコリーは小房に分ける。沸騰したお湯に塩一つまみ(分量外)を入れて約2分間下ゆでをし、ザルにあけておく。 |
 |
フライパンにごま油とみじん切りにした長ネギを入れ、弱火から中火ですきとおるまで炒める。 |
 |
4にカキを下味ごと入れ、2の合わせ調味料を加え、ふたをして中火で約5分間、弱火にしてさらに約5分間蒸し煮する。ふたを開けて煮汁をからめる。 |
 |
3のゆでたブロッコリーを加えて強火にし、全体になじませてから2の水溶き片栗粉を入れて、とろみをつける。 |
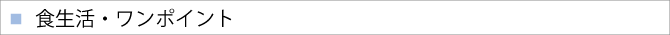
肝臓にやさしい食生活
肝臓は、私たちの体にとって重要な役割を担う臓器です。「沈黙の臓器」と言われるように、何らかのダメージを受けても痛みなどの自覚症状が現れにくいのですが、だからといって肝臓のケアを怠るのは禁物です。
肝臓病の主な原因は、ウイルス、アルコールの過剰摂取、肥満などです。肝臓病になってしまった場合の食事は症状により異なりますが、肝臓を守る食生活のポイントは、次のとおりです。
 |
バランスのとれた食生活を送る
食事でとったカロリーが消費量を上回ると、肝臓に中性脂肪がたまる脂肪肝になりやすくなります。また、たんぱく質の合成を行う重要な働きがある亜鉛が欠乏すると肝臓の代謝不良となり、慢性肝疾患へ移行すると言われています。今回使用するカキは、亜鉛を多く含む食品です。 |
 |
1日3食を守り、規則正しい食生活を送る
食事の回数が少ないほど体に脂肪がたまりやすく、肝臓に負担をかけてしまいます。 |
 |
良質なたんぱく質を摂取する
肝機能が低下するとたんぱく質の貯蔵量が減るため、良質のたんぱく質を補って肝臓を修復させる必要があります。特に大豆に含まれる大豆サポニンは肝機能を高める作用があると言われています。 |
 |
アルコールはほどほどに
アルコールが肝臓で分解されるときにできるアセトアルデヒドは毒性があり、肝細胞にダメージを与えます。1日分のアルコールの適量は男性40g、女性20g程度までで、週2日の連続した休肝日を作ることが重要です。 |
 |
体重管理
BMIが適正範囲におさまるよう、肥満の原因となる食べすぎ等に注意しましょう。 |
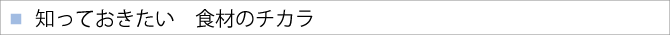
カキ
カキは、”海のミルク“と言われるくらい栄養価が高い魚介類です。100gあたりの栄養価は表のとおりで、特に脂質の代謝やたんぱく質の合成に必要な亜鉛が多い食材です。「日本人の食事摂取基準(2015年版)」によると、亜鉛の1日の摂取基準は成人男性8㎎、女性6㎎で、カキを40g~55g食べれば1日分の亜鉛をとることができます。
亜鉛が不足すると味覚異常を起こすと言われています。舌にある味覚細胞は常に新しく生まれ変わり、再生には亜鉛が重要な役割を果たしています。亜鉛が不足すると味覚細胞の再生ができなくなってしまうのです。 |
 |
| カキは二枚貝のため、ノロウイルス汚染の恐れがあります。ノロウイルスは熱に強いため、調理時はしっかり加熱する必要があります。具体的には中心部が85℃~90℃で90秒以上の加熱です。加熱温度に注意して調理しましょう。 |
| |
| 表 カキの栄養価(養殖100gあたり) |
| エネルギー |
エネルギー |
脂質 |
炭水化物 |
カルシウム |
鉄 |
| 70kcal |
6.9g |
2.2g |
4.9g |
84mg |
2.1mg |
| 亜鉛 |
ビタミンA |
ビタミンB1 |
ビタミンB2 |
ビタミンC |
食塩相当量 |
| 14.5mg |
24µg |
0.07mg |
0.14mg |
3mg |
1.2g |
|
[レシピ考案・監修] 相模女子大学短期大学部食物栄養学科 准教授
管理栄養士 井上 典代



