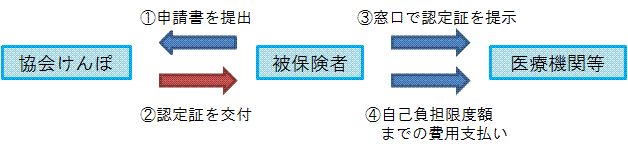医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に申請いただくことにより1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
(※)保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
また、同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
方法①マイナ保険証を利用する
方法②限度額適用認定証を利用する
70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について
|
平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。) |
◆自己負担限度額
受診者の年齢および被保険者の所得区分によって下記のとおり分類されます。
70歳未満の方の区分
|
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当※2 |
| ①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% |
140,100円 |
| ②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% |
93,000円 |
| ③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% |
44,400円 |
| ④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 |
44,400円 |
| ⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
24,600円 |
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上75歳未満の方
| 被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
|||
|
外来 |
外来・入院 |
|||
|
(個人ごと) |
(世帯) |
|||
| ①現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数該当:140,100円] | ||
| 現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数該当:93,000円] | |||
| 現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数該当:44,400円] | |||
|
②一般所得者 |
18,000円 |
57,600円 |
||
|
[多数該当:44,400円] |
||||
|
③低所得者 |
Ⅱ(※3) |
8,000円 |
24,600円 |
|
|
Ⅰ(※4) |
15,000円 |
|||
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
◆限度額適用認定証を利用する場合の流れ
① 限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出してください。
② 限度額適用認定証を交付します。(発行までの目安・・・1週間程度)
③ 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します。
④ 同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。