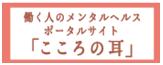救急医療の適正利用にご協力をお願いします
令和02年12月22日
救急医療の現状
近年、「夜間のほうがすいてそうだから」「昼間は仕事があるから」など、軽症の患者さんがあえて休日や夜間に病院の救急外来を受診し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しています。いわゆる「コンビニ受診」が増加すると、救急医療を担う医師や医療スタッフの負担をますます重くし、地域の救急医療体制が維持できなくなる恐れがあります。
ご自身が万が一急病になったときなどに、安心して救急医療が受けられるように、また最終的に保険料や窓口負担として皆様にご負担いただく医療費を有効に活用するため、日ごろの病院などのかかりかたを再度チェックしてみましょう。
1.日ごろの病院などのかかりかたを再チェック!
できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。
昼間の診療時間内は外来の患者さんを診るために必要な医師や看護師、検査技師、薬剤師などの医療スタッフも十分に揃っていますので、検査や投薬などもスムーズに受けられます。一方で、休日や夜間の時間外の診療は、あくまで緊急事態に備えた少人数体制で対応することになります。また、診療時間帯以外で診察を受けると時間帯加算がプラスされますので、窓口負担が増えてしまいます。体調が悪いときは早めに診てもらいましょう。
救急医療は、病気の程度により医療機関の役割が異なります。
休日や夜間の時間外受診は、病気の程度に応じて医療機関の役割が分かれています。重症患者を救うための高度な救急医療を担う病院へ、緊急性の無い患者が多く訪れてしまうと、一刻を争う重症の救急患者の対応が難しくなります。また、対応する医師や医療スタッフの負担もますます過重なものとなってしまいます。症状が軽い場合は、休日の在宅当番医や夜間急病センターで診てもらいましょう。
なお、宮崎県における救急医療施設は以下のように役割が分かれています。
| ■初期救急医療施設・・・主に入院治療を必要としない軽度の救急患者の治療を行います。 | |
| ◆(休日昼間)在宅当番医 ・・・日曜、祝日、年末年始(12月30日〜1月3日)の昼間、一般の 病院と診療所が当番を決めて診療にあたっています。
☆在宅当番医は、宮崎医療ナビ(宮崎県総合医療情報システム)(外部リンク)で検索することができます。 また、市町村のホームページ、医師会のホームページにも掲載されています。 | |
| ◆(夜間)夜間急患センター ・宮崎市夜間急病センター ・都城救急医療センター ・延岡市夜間急病センター ・日南市初期夜間急病センター | |
| ■第二次救急医療施設・・・休日、夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の治療を行います。 (救急告示施設) | |
| ■第三次救急医療施設・・・生命の危険に瀕している状況で、高度な医療が必要なときに対応します。 (救急救命センターなど) 初期救急医療、第二次救急医療施設からの転送患者を受け入れる後方病院 であり、高度の検査・手術を要する重篤救急患者の救命医療を行います。 ・県立宮崎病院 ・県立延岡病院 ・宮崎大学医学部付属病院(救急部) |
かかりつけ医はおもちですか?
昼間の診療時間内にかかるときも、最初から大病院を受診したほうが安心と思いがちですが、身近で信頼できる「かかりつけ医」をもたれるとより安心です。
<かかりつけ医をもつメリット>
- 普段から受診し、健康についての相談にのってもらうことで信頼関係を築けます。
- 普段から受診することで、健康状態や生活環境などを把握してもらえます。その情報を1か所で管理しておくことで2重の検査の防止になります。また、病歴や体質などの情報を管理されていることにより、より適切な治療やアドバイスを受けることができます。病気の予防、早期発見、早期治療にもつながります。
- 必要に応じて専門医や適切な医療機関を紹介してくれます。かかりつけ医からの紹介で高度な医療を担当する病院を受診されると、よりスムーズな治療を受けることができます。
<かかりつけ医を選ぶときのポイント>
- 相性が合う、相談しやすい
- 自宅や勤務先から近いこと
- 分かりやすい説明をしてくれる など
<いきなり大病院へ行くと、初診時に別料金がかかります(保険外併用療養費【選定医療】)>
- ベッド数が200床以上の病院へ、紹介状(診療情報提供書)を持たずに初めてかかる場合は、原則として病院の定める特別料金がかかります。からだに不調を感じた時は、まずは「かかりつけ医」にご相談されることをお勧めします。
<さがしてみましょう>
- 地域の医療機関が検索できます。→宮崎医療ナビ(宮崎県総合医療情報システム)(外部リンク)
2.医療に関する各種相談窓口などがあります。
医療機関以外にも、さまざまな相談窓口や参考になるホームページがあります。その一部をご紹介します。
| 子ども救急医療電話相談(#8000) | (厚生労働省研究班/日本小児科学会監修) |
| 夜間、お子さんの急な症状で心配なったとき、「#8000」をプッシュすると、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、お子さんの症状に応じた対処の仕方などのアドバイスが受けられます。 | お子さんの気になる症状から様子を見ていいのか、すぐに病院へ連れて行くほうがいいのかの判断の目安が示されます。 |
| (厚生労働省委託事業/財団法人産業医学振興財団) | (宮崎県精神保健福祉協議会/宮崎県精神保健福祉センター) |
|
| |
| 事業所のご担当の方、上司、同僚の方など、働く方を支援する方にも役立つ情報があります。 事業所のご担当の方、上司、同僚の方など、働く方を支援する方にも役立つ情報があります。 | さまざまな悩みや心配事、心の病気を抱えている方のために、相談窓口や生きがいづくりの場などを案内する宮崎県民向け情報のサイトです。 |