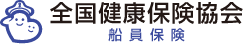- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
★・‥…―――――――――――――――――――――――――――――…‥・★
全国健康保険協会 船員保険部メールマガジン「うみがめ〜る」
こんにちは、全国健康保険協会 船員保険部です。
船員保険部メールマガジン「うみがめ~る」は
加入者の皆さまにとってお役に立つお得な情報をお届けします。
┏━━━┓
┃\_/┃ [TOPICS]
┗━━━┛
■1■ 健診をまだ受診していない方はお早めに!~生活習慣病予防健診のご案内~
□2□ もう使いましたか?「電子処方せん」
■3■ 船員保険に加入したらまず登録!船員保険健康アプリ
□4□ 船員の働き方改革について
■5■ 令和6年能登半島地震における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について
┌─┐
│1│健診をまだ受診していない方はお早めに!~生活習慣病予防健診のご案内~
└─┴───────────────────────────────────
船員保険では健診費用の補助をおこなっています。
船員保険に加入されている方は、年度内に1回、無料で健診を受けることができます。
今年度の健診をまだ受診していない方は、ぜひ「生活習慣病予防健診」をご利用ください。
【生活習慣病予防健診の4大メリット】
○無料で受診できます!
※一般健診・巡回健診が対象
○船員手帳の健康証明を同時に受けることができます!
※一部例外機関があります。また、別途費用がかかります。
○健診費用の大幅なコスト削減が見込めます!
○各種がん検診(胃・肺・大腸・子宮頸がん・乳がん)を無料で受診できます!
※子宮頸がんは偶数年齢の女性、乳がん検診は40歳以上の偶数年齢の女性が対象です。
【対象者】
○ご本人(被保険者)の方:35歳~74歳
○ご家族(被扶養者)の方:40歳~74歳
※75歳以上の方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※ご家族(被扶養者)の方は、手軽に受診したい方向けの「特定健康診査」をお選びいただけます。
▼生活習慣病予防健診についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g4/cat410/
▼特定健康診査(ご家族(被扶養者)の方向け)についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g4/cat410/R30318_2/210311_1/
┌─┐
│2│もう使いましたか?「電子処方せん」
└─┴───────────────────────────────
「電子処方せん」とは、これまで紙で発行していたお薬の処方せんを電子化したものです。
【電子処方せん3つのメリット】
①今まで以上に安心してお薬を受け取れる!
複数の医療機関・薬局の過去のお薬情報を医師・薬剤師と共有できます。同じ成分のお薬をもらうこと(重複投薬)や良くないお薬の飲み合わせを防ぎ、安心安全な医療に繋がります。
②自分のお薬情報をいつでも確認できる!
マイナポータルでご自身の直近のお薬情報を確認することができます。また、市販薬を買う際の飲み合わせの確認等にも活用できます。
③診療やお薬の受け取りが便利になる!
処方せんが電子化されるため、薬局に処方せん情報をあらかじめ送ることができます。お薬の受け取りまでの待ち時間を短縮できたり、処方せんを紛失する心配がなくなります。
【電子処方せんを利用するための大きな3step】
Step.1 医療機関の窓口で電子処方せんを選択
Step.2 電子処方せん対応薬局で受け付け
Step.3 調剤されたお薬を受け取る
▼詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
▼電子処方せん対応の医療機関・薬局はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
┌─┐
│3│船員保険に加入したらまず登録!船員保険健康アプリ
└─┴────────────────────────
「船員保険健康アプリ」をご存じですか?
健診結果や健康情報が確認できる、船員保険加入者様限定のスマートフォン向けアプリです。
「船員保険健康アプリ」で健康への第一歩!
○ご自身の健診結果をいつでも閲覧可能!
○健診結果に合わせた個別のアドバイスで生活習慣を改善できる!
○船員保険部からの制度改正等の最新情報をいち早く受け取れる!
○医師や著名人による多彩な健康情報を毎日更新!
このほか、歩数の記録など、健康をサポートする機能が充実!
ぜひご自身のスマートフォンへダウンロードしてお使いください。
※初回登録時に必要な保険者番号は「02130011」です。
【ご利用いただける方】15~74歳の船員保険加入者様
【注意点】
船員保険の生活習慣病予防健診、特定健診、または船員手帳の健康証明書の写しの提出を行っていない場合、アプリに健診結果が反映されません。まだお済みでない方は健診の受診等をご検討いただきますようお願い申し上げます。
▼詳しくはこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/240613apurichirashi.pdf
┌─┐
│4│船員の働き方改革について
└─┴─────────────
令和5年4月1日から、船員の働き方改革のため、労働時間規制の見直しや健康確保の新たな制度がスタートしました。
【主な内容】
◇防火操練、救命艇操練その他類似の作業、航海当直交代の引継ぎ作業が労働時間規制の対象に
◇常時使用する船員の健康証明書検査で、指定医の診断結果に基づく健康管理を
◇常時50人以上の船員を使用する船舶所有者の皆様への産業医の選任義務など
▼労働時間規制の見直し等の働き方改革の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000026.html
▼健康確保の新たな制度の詳細
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html
その他に、船舶所有者、船員の皆さまで、労働条件などお困りごとがありましたら、
地方運輸局の「船員労働の総合相談窓口」まで、メール等でお気軽にご相談ください。
▼窓口のご利用方法
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001488541.pdf
┌─┐
│5│令和6年能登半島地震における保険証の取り扱いと一部負担金の免除について
└─┴───────────────────────────────────
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、以下の項目を医療機関の窓口で申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。
○ 氏名
○ 生年月日
○ 連絡先(電話番号等)
○ お勤め先の名称(船舶所有者名)
また、令和6年1月1日~令和6年9月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されます。
【免除の対象となる方】
以下の1と2の両方に該当する方
1.令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
2.令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
○ 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
○ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
○ 主たる生計維持者の行方が不明である方
○ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
○ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【受診・利用の流れ】
医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について、支払いが不要となります。
【免除対象期間】
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護
▼令和6年能登半島地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)
https://www.bousai.go.jp/index.html
▼免除・還付についてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/event/sinnsai/r060103/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
★・‥…―――――――――――――――――――――――――――――…‥・★
- バックナンバーVol.120(2025年6月4日発行)
- バックナンバーVol.119(2025年5月21日発行)
- バックナンバーVol.118(2025年5月7日発行)
- バックナンバーVol.117(2025年4月17日発行)
- バックナンバーVol.116(2025年4月3日発行)
- バックナンバーVol.115(2025年3月19日発行)
- バックナンバーVol.114(2025年3月5日発行)
- バックナンバーVol.113(2025年2月5日発行)
- バックナンバーVol.112(2025年1月8日発行)
- バックナンバーVol.111(2024年12月4日発行)
- バックナンバーVol.110(2024年11月6日発行)
- バックナンバーVol.109(2024年10月3日発行)
- バックナンバーVol.108(2024年9月4日発行)
- バックナンバーVol.106(2024年7月9日発行)
- バックナンバーVol.105(2024年6月5日発行)
- バックナンバーVol.104(2024年5月7日発行)
- バックナンバーVol.103(2024年4月3日発行)
- バックナンバーVol.102(2024年3月5日発行)
- バックナンバーVol.101(2024年2月5日発行)
- バックナンバーVol.100(2024年1月9日発行)
- バックナンバーVol.99(2023年12月5日発行)